『いのちを”つくって”もいいですか?』 島薗進
ちょっとどきっとするタイトル。
「いのちを”つくって”もいいですか?」の読書会に参加してきました。
本を読んだ直後の感想は、とにかく「もやもやする」。
正しい解答がないけど、考えることを放棄してはならない内容だけに、更に考える。でも、どうしたらよいか、やっぱり答えがでない。でも、将来的に確実に答えが必要なものだと分かっているから、もやもやするわけです。

この本を読んだ後の私の命題は「出生前診断で障害があるとわかった時、自分は生み育てることができるか?」ということ。
社会全体のこととして、障害者がより生きやすい環境が必要だね、って思う一方で、出生前診断で障害を持つ可能性があると診断されたら、自分ならどうするんだろう?と思う。生み育てる選択を、果たしてできるだろうか?
まだまだ先の話のように思えるバイオテクノロジーの先端技術だけど、実はすでに始まっているものがある。それは出生前診断。具体的な数字を知り、現実がひたひたと知らないところで進んでいることに、おののく。
海外だとそれは更に顕著で、イギリスやフランスの例を聞いて、ぞっとした。
出生前診断を受け、陽性の人が中絶する率が高くなることで、ダウン症の子が減っているという。
そこには、障害がないことが良いことだ、という前提がある。それは、誰が決めたのだろう?
生まれてはいけないいのちがあるのか?と問うたら、ない、と答えるのがよしとされる社会なのにも関わらず。
でも、そこでまた、最初の命題に戻るのだ。
自分の子どもが障害を持つと妊娠中にわかっていたら、果たして生む決断をそのときに私はできるだろうか?障害があってもいい、と思えるだろうか?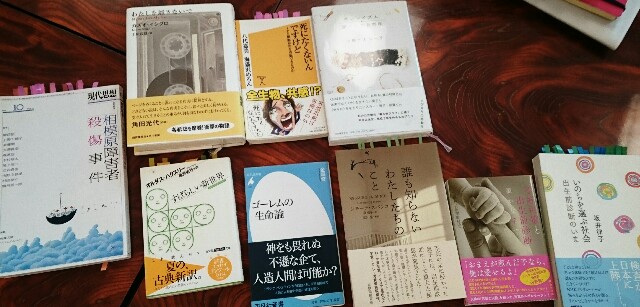
ひとりだと同じところでつまづいてしまうこの問いに、他の参加者さんの発した言葉は、こうだった。
生む、と決断できないのは、不安だからだよね。
その子が安心して育つことのできる社会って、どんなところだろう?
そんな意見を聞いて、はっとした。
どういう社会なら、障害があっても、生み育てられる、と思えるだろう?
そんな風に考えたことがなかったから。
そうか、障害児を育てることに不安のない社会だったら、生もうと思えるかもしれない。
そして、すでに健康な子どもがいて、今後妊娠の予定がない自分には、この命題にどんな答えを出しても、当事者として悩む必要のない自分であるがゆえに、きれいごとの答えになってしまうと思いこんでいたけど、そうじゃなかった、と思った。
この社会の構成員である限り、当事者なのだ。
別の参加者さんが言っていた。「みんな当事者なんです」って。男性も女性も老いも若きも、みんな社会の構成員。今すれ違った人が、正に障害を持っている人かもしれない。目の前の人の家族が、障害を持っているかもしれない。つながっているいのち。
どんな社会で生きたいのか、それには自分は何をしたらよいのか。
そこを考えて、身近なところから行動することが、私の命題の答えになる。
遠回りなようだけれど。
答えのヒントが得られたことが、大きな収穫でした。これは、真剣にこのことを考える時間をとれた成果。ひとりではなく、9名で、真摯に思考を重ねた結果。
私以外の皆さんも、きっと何かみつかったのではないかな。
この場を開催してくれた主催のお二人に感謝。
そして参加者の皆さま、真摯な2時間の思考タイムを共有してくださってありがとうございました。